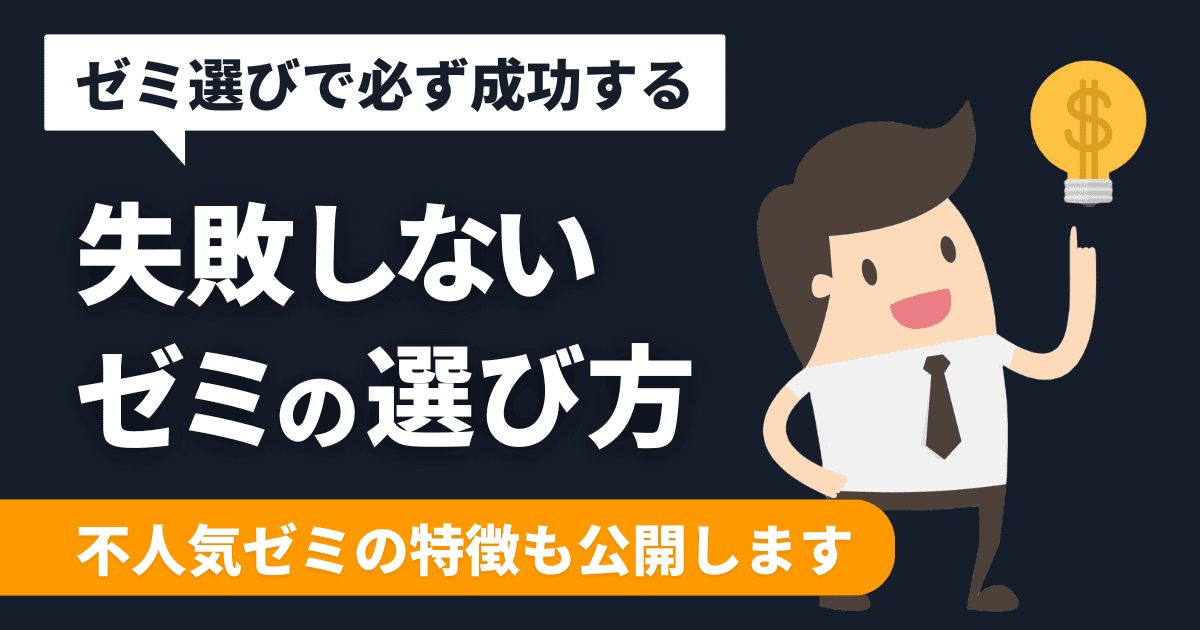こんな疑問を解決します。
この記事の内容
今回は『文系の大学生に向けて、ゼミの選び方を5つ紹介』というテーマです。
大学のゼミの選び方5つ
- ゼミ選考の倍率がそこそこ高い
- サークルやバイトの先輩がいる
- ゼミの雰囲気が自分に合っている
- 研究テーマがシンプルにおもしろい
- 教授が就職のコネを多く持っている
結論は、上記のとおり。
ぶっちゃけ、この選び方でOKです。
こういった背景の僕が、今回はゼミの選び方について解説します。なお、後半では「文系の大学でよくある不人気ゼミの特徴」や「NGな選び方3つ」もご紹介しているので、最後までどうぞ。
前置きはさておきですね。
では、いきましょう (`・ω・´)
文系の大学生に向けて、ゼミの選び方を5つ紹介【不人気はNG】

冒頭でお見せしましたが、下記5つの選び方。
- ゼミ選考の倍率がそこそこ高い
- サークルやバイトの先輩がいる
- ゼミの雰囲気が自分に合っている
- 研究テーマがシンプルにおもしろい
- 教授が就職のコネを多く持っている
では、順に説明していきますね。
その①:ゼミ選考の倍率がそこそこ高い
シンプルに「ゼミ選考の倍率が高い = 他の大学生から人気」ですよね。
逆に言えば、選考倍率が低すぎると、不人気ゼミの可能性ありです。なので、そこそこの選考倍率があるゼミの方が、入ってからの後悔はグッと減るはずですよ。
おすすめの目安倍率
上記のとおり。
倍率ごとの特徴もご紹介します。
- 1倍から2倍:不人気ゼミかも
- 3倍から4倍:ちょうどいい
- 5倍よりも上:難易度が高すぎ
もちろん、選考倍率だけで判断するのは選び方としてNGです。一方で、倍率ごとに特徴があるので、1つの目安にするのはありかなと思います。
その②:サークルやバイトの先輩がいる
[雰囲気を詳しく聞ける]&[選考対策をしてくれる]ので、わりと神です。
友達の先輩でもOK
僕はサークルに入っていなかったので、先輩はゼロでした。その代わり、友達の先輩が第一志望のゼミにいたので、選考対策の情報などを教えてもらっていました。
- どんな特徴の大学生を求めているか
- 実際の雰囲気は、どんな感じなのか
- 1日のスケジュール感は忙しいのか
このあたりをマルっと聞けたので、感謝です。中でも『どんな特徴の大学生を求めているか』は選考を受ける上でポイントですよ。
選考で1番大切なこと
こちらのとおり。つまり『どんな特徴の大学生を求めているか』がわかれば、その特徴に合わせにいけますよね。たとえば[ポジティブな人を求めている]なら、ポジティブな雰囲気を出す感じ。
なので、選び方として「サークルやバイトの先輩がいること」はわりと重要です。もちろん、友達との先輩や知り合いでもOKなので、このあたりはリサーチが必要かもです。
その③:ゼミの雰囲気が自分に合っている
ぶっちゃけ、これが1番大切です。
なぜなら、雰囲気が合っていないと、マジで日々の活動がキツいから。
雰囲気が合わないゼミがあった
僕自身、研究テーマ的に「どうしても入りたいな...」と思うゼミがあったんですよね。しかし、説明会に行ってみると、、、リアルガチな陽キャラ(= ワイワイ系)しかいなくて絶望しました。
おそらく、そのまま選考を受けていたら、僕の雰囲気的に落ちていたと思います。もし受かっていても、2日目くらいで辞めていたはず。
なので、資料や情報だけで選ぶのはNGでして、必ず雰囲気をチェックするために、説明会や相談会などに参加した方がいいかもです。
その④:研究テーマがシンプルにおもしろい
これはマジで重要 of 重要です。
理由はシンプルでして、研究テーマが面白くないと、研究が地獄だからですね。
経済学部の場合
■ 面白そうな研究テーマ
・行動経済学:行動に基づいた経済学
・地域経済学:地域に基づいた経済学
■ 少し苦手な研究テーマ
・数理経済学:数学がメインの経済学
・理論経済学:経済史が中心の経済学
僕の場合は、こんな感じでした。大きな特徴としては[面白そう = プロジェクトをみんなで協力して進める研究テーマ]で[苦手 = 1人だけで計算や学習を進める研究テーマ]でした。
このあたりは大学や学部、人の特徴によって変わってくるので、下記の3ステップで選び方を実践するといいですよ。
おすすめの手順
- 学部内のゼミをリストアップする
- それぞれの研究テーマを調べる
- 面白そう、苦手の2軸で分ける
上記のとおり。
すぐにできる選び方なので、おすすめです。
その⑤:教授が就職のコネを多く持っている
優先度は低めですが、選び方の1つとして、就職のコネは大切かもですね。
強み = 就職のコネだけは危険
たとえば、強みや特徴として、下記のみをアピールしている場合は危険ですよ。
- 〇〇商事:7名
- 〇〇銀行:5名
- 〇〇証券:3名
それよりも、強みとしてアピールはしていないけれど、ゼミ生の話や噂などで「就職が強い」とか「教授が就職のコネを持っている」などがあれば、わりと信頼性が高いかなと思います。
選び方の失敗例:GPA 重視のゼミを志望する
GPA 重視のゼミに入った友達で、幸せな人が0人だったので書きました。
GPA を重視する例:応募資格
僕が卒業した同志社大学だと、評定(= GPA)は最大で4でした。つまり、GPAが3.5以上というのは、わりと神レベルな大学生です。
なぜ選び方でGPA 重視がNGかと言うと『GPA が高いゼミ = 自分に合うとは限らないから』ですね。繰り返しですが、選び方で1番重要なことは、あなたに合っているかどうかです。
自分に合わないと、シンプルに研究が地獄になるので「合っているか」は大切。
ちなみに、入っちゃった後に「選び方で失敗したわ...」という大学生に向けて【後悔】ゼミ選びに失敗した理由+対処法5つ【入るゼミを間違えた】という記事を書きました。ぶっちゃけ、大学生活はゼミだけじゃないので、気にしなくてOKです。
文系の大学でよくある『不人気ゼミの特徴』を5つ解説します

お次は、不人気ゼミの特徴ですね。
- ゼミの研究テーマがニッチすぎる
- 「楽すぎる」or「厳しい」が極端
- ゼミの雰囲気がハイパー悪すぎる
- 選考の倍率が他と比べて極端に低い
- 日々の活動がシンプルに面白くない
上記を意識すれば、うまく回避できるはず。
というわけで、1つずつ解説をしていきます。
特徴①:ゼミの研究テーマがニッチすぎる
研究テーマがニッチすぎると、自然と不人気になりやすいかなと思います。
なぜなら、多くの大学生にとって、あまり面白さを感じられないからですね。
あなたにとって面白ければOK
とはいえ、研究テーマがニッチすぎるというのは、あくまで客観です。あなた自身の視点(= 主観)で、研究テーマが面白そうなら、入っても問題なしですよ。
これは就職活動も同じかもですが「周りの人から羨ましいと思われる企業」とか「シンプルに大学生から人気な企業」を目指しすぎると、入ってから疲れます。なんせ、自分の軸がないから。
特徴②:「楽すぎる」or「厳しい」が極端
下記2つのゼミは、わりと危険です。
極端に楽すぎる
極端に厳しい
上記のとおり。
つまり、バランス感覚が大切ですね。
僕が入っていたゼミ
- 研究:やるときはガッツリやる
- 課題:ぶっちゃけ、かなり少ない
- 発表:1ヶ月に1回くらいのペース
このあたりは大学生によりけりかもですね。たとえば「マジで楽に単位が欲しい」とか「ゴリゴリに厳しい方がいい」などの好みがあるかもです。
僕の場合は『ほどよく忙しくて、そこそこ楽しみたい』というわがままな大学生だったので、ワークライフバランス的なやつがいい感じのゼミに入りました。
バランスがいいゼミに入った結果
こちらのとおりでして、6人ほどのプロジェクトチームで夜遅くまで研究する日もあったし、発表会などが終わった後はタコパとかしました。わりと大学生っぽい生活ができました。
なので「楽すぎる」or「厳しい」が極端すぎるのは選び方としてはNGです。加えて「楽すぎる」or「厳しい」が極端だと、不人気の可能性も高いですからね。
特徴③:ゼミの雰囲気がハイパー悪すぎる
雰囲気が悪い = 不人気の特徴です。
当たり前かもですが、わりとよくありますよ。
説明会などで確認すべきこと
- ゼミ生たちが、お互いフレンドリー
- 教授からゼミ生に対しての接し方
- 全体的な雰囲気が感覚で良いか
こちらのとおり。注目すべきは[ゼミ生 → ゼミ生の雰囲気]と[教授 → ゼミ生の雰囲気]です。どちらもいい感じの雰囲気なら、わりといいかもです。
一方で、どちらの雰囲気も最悪なら、おそらく不人気の可能性が高め。入ると99%くらいの確率で、後悔しちゃうかもです。
特徴④:選考の倍率が他と比べて極端に低い
選考倍率が低すぎるゼミは、不人気な可能性が高いかもです。
なぜなら、人気なゼミは、自然と選考倍率が高くなるからですね。
大学と同じです
・不人気な大学 → 倍率が低い
僕自身が「ランク」とか「Tier」とかの言葉が好きなので「人気」とか「不人気」も好きです。不快に思われた方がいたら、マジでスイマセン m(_ _)m
なので、不人気ゼミを避けるなら、選考倍率が[3倍から4倍くらい]を狙うといいかもです。ちなみに、選考倍率ごとの特徴を簡単にまとめたので、下記を参考にどうぞ。
- 1倍から2倍:不人気ゼミかも
- 3倍から4倍:ちょうどいい
- 5倍よりも上:難易度が高すぎ
選考倍率が3倍から4倍くらいは、バランスがいい印象です。具体的には、研究などをしっかりとしつつも、ほどよく楽しめるといった感じです。まさに大学生がイメージするゼミですね。
なお、選考倍率が上がるにつれて、その分だけ選考基準も厳しくなります。詳しくは【余裕】大学のゼミの選考基準とは?【結論:キャラ作りが大切です】で解説しているので、こちらもセットでどうぞ。
特徴⑤:日々の活動がシンプルに面白くない
これは最悪ですよね。
まさに不人気 of 不人気の特徴です。
面白くないと感じるゼミの特徴
- 研究テーマに興味を持てない
- 活動の内容が毎日同じで単純
- 教授の雰囲気が自分と合わない
ゼミって思っているより、1週間の中で時間を使いますからね。なので、日々の活動が面白くないと、その分だけ地獄なので、このあたりは要チェックです。
なお、1週間のスケジュールについては、本記事の『選び方のポイント:活動のスケジュールに無理がないか』で解説しているので、こちらの見出しへジャンプをどうぞ。
ゼミの選び方に悩む大学生に向けて、ポイント+コツをご紹介

選び方についての、ポイントも解説しますね。
- 教授と自分が性格的に合っているか
- 友達も一緒に同じゼミに入れそうか
- ゼミの就職先が自分の目指す企業か
- 活動のスケジュールに無理がないか
こちらの4つですね。
では、順に説明していきます。
ポイント①:教授と自分が性格的に合っているか
教授との相性は、ゼミに入る前と入った後の両方で影響します。
例:教授との相性
・入った後:活動の際に影響する
入ってからも重要かもですが、まずは入る前の選考ですよね。
実体験:僕の友達は相性で落ちた
友達が受けていた選考は[ゼミ生の評価]と[教授の評価]の2つが軸としてありました。前者は満点だったのですが、後者は点数が低くて、落ちちゃったんですよね。
つまり、選考基準に教授からの評価がある場合、必ず相性の確認は必要ですよ。とはいえ、相性の確認はシンプルでして「この人キツイな...」と思ったら、合わない可能性大です。
説明会に参加して、教授との相性が悪そうなら、違うゼミの方がいいかもです。
ポイント②:友達も一緒に同じゼミに入れそうか
僕は友達ゼロで入ったのですが、やっぱり友達と入るべきでした。
というのも、僕が入ったときに、すでにグループができていたからですね。
僕自身、あまりコミュニケーションが得意な方ではないので、最初はわりとキツイ感じでした。なので、友達と入れるなら一緒に入った方が、気軽に相談もできますし楽しいと思います。
ポイント③:ゼミの就職先が自分の目指す企業か
僕は重視していませんでしたが、就職の視点も選び方としてはありかもです。
公開している例
- 〇〇商事:7名
- 〇〇銀行:5名
- 〇〇証券:3名
上記のように、就職実績などを公開しているゼミもありますからね。もし、あなたが目指している企業があるなら、そのゼミに入ると、就職のコネや選考対策も知れるので、わりとあり。
とはいえ、選び方としては優先度は低くてOKです。というのも、就職活動はコネよりも『自分でいかに頭で考えつつ、行動できるか』がポイントだからですね。
実際、僕は途中でゼミを辞めましたし、サークルにも入ってない系の大学生でしたが、普通に大手企業から内定をゲットしましたからね。なので、就職の観点で、ゼミを選ぶのは優先度としては低め。
ポイント④:活動のスケジュールに無理がないか
もっと簡単に言うなら「キツすぎず、楽すぎないか」といった感じです。
というのも、ゼミによって1週間あたりの忙しさが違ってくるからですね。
僕が入っていたゼミのスケジュール

Inatatu:ゼミのスケジュール
上記のとおり。スケジュールや忙しさは、マジでゼミによりけりです。なので、説明会や相談会に参加しつつ『1週間あたり、どれくらい活動に時間を使うか』を必ず聞いておくべきですよ。
※最初に聞きまくっておけば、入ってから「キツすぎて絶望...」とか「逆に物足りなくね?もっと研究してぇ」といった、ギャップを減らせますからね。
やると99%の確率で後悔しちゃう、絶対NGなゼミの選び方3つ

最後は、NGなゼミの選び方ですね。
- 選び方を友達に全て任せてしまう
- 「ゼミ = 楽な方がいい」が最優先
- マジで適当にゼミを選んでしまう
ぶっちゃけ、上記3つを意識すればOK。
それでは、順に解説をしますね。
NG①:選び方を友達に全て任せてしまう
友達に全任せはNGです。
なぜなら、後悔する可能性が高いから。
友達に任せた末路
もちろん、友達がいるので楽しいかもです。ただ、選び方で1番重要なポイントは「あなたが熱中できる研究テーマかどうか」です。
繰り返しですが、僕がおすすめする選び方は、次のとおりです。
大学のゼミの選び方5つ
- ゼミ選考の倍率がそこそこ高い
- サークルやバイトの先輩がいる
- ゼミの雰囲気が自分に合っている
- 研究テーマがシンプルにおもしろい
- 教授が就職のコネを多く持っている
[友達がいる]という要素も選び方では大切かもです。ポイントは優先順位でして「まずはあなたが優先したいことを書きまくる」→「それぞれに優先順位を付ける」の流れでOKです。
NG②:「ゼミ = 楽な方がいい」が最優先
[楽な方がいい]という軸は、選び方で捨てた方がいいかもです。
理由はシンプルでして、楽すぎると得られるものがゼロに近いからですね。
得られるものが少ないと就活で詰む
就職活動で、下記の質問が聞かれます。
つまり、活動の中で得られた経験や学びのことでして、楽すぎるゼミに入っちゃうと、経験や学びがほぼゼロです。というのも、授業や活動に参加していれば、単位がもらえちゃうからですね。
大学生によって考えが分かれるポイントなので、あなたが『ゼミに求めること』を考えればOK。「単位を取れたらそれでいいや」といった感じなら[楽な方がいい]という軸は選び方で神。
NG③:マジで適当にゼミを選んでしまう
適当に選ぶと、99%の確率で後悔します。
適当に選んでしまった末路
- 興味のない研究テーマで苦労する
- ゼミの雰囲気に馴染めずに絶望する
- 仲良くなれる友達がゼロでぼっちへ
末路としては、こんな感じ。
良くも悪くもゼミって大学生活で1度きりなので、後悔しない選び方をどうぞ。
ちなみに「ゼミって入らなくても良くね?」という大学生に向けて【最高】大学でゼミに入らなくてよかったと思う5つの理由を公開するといった記事を書きました。気になる方はどうぞ。
まとめ:ゼミの選び方と不人気ゼミの特徴を確認しまくろう

今回は『文系の大学生に向けて、ゼミの選び方を5つ』を紹介しました。
大学のゼミの選び方5つ
- ゼミ選考の倍率がそこそこ高い
- サークルやバイトの先輩がいる
- ゼミの雰囲気が自分に合っている
- 研究テーマがシンプルにおもしろい
- 教授が就職のコネを多く持っている
上記のゼミの選び方を実践すれば、わりと失敗しないゼミ選びができるはず。
なお、どのゼミの選考を受けるか決まった後は【10分の想定】ゼミ面接の質問で聞かれること【ゆるい服装でOK】を読みつつ、選考対策をすればOK。
それでは、最高のゼミライフをどうぞ。
今回は以上です。